株取引の確定申告を解説します。証券口座の種類と確定申告、投資家の給与所得の状況の違いから異なる手続きを説明します。確定申告を行うことで投資家が得ることができる可能性があるメリットお教えします。具体的な申告書の記入についても言及しますので、きちんと理解して脱税とならないようにきちんと確定申告を行っていきましょう。
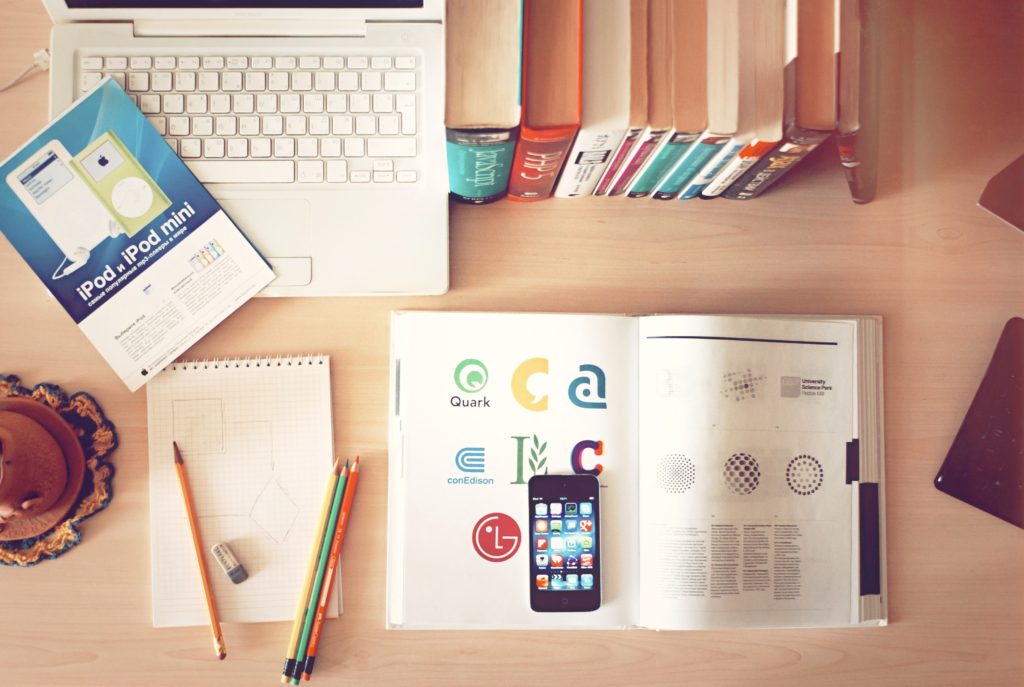
株の利益と税金
株式投資の利益と税金について説明します。株式投資の利益に対する税金にはどのようなものがあり、どのように計算されるのでしょうか。
株の利益の計算方法
株式投資では、株式の金額が購入時よりも売却時の方が高かった場合に利益が発生し、以下の計算式で求められます。
売却金額ー購入金額(株式購入価格+購入手数料)ー売却手数料=利益
購入時にかかった手数料も含めた総額と、売却時の手数料を考慮して利益額が算出されます。
利益にかかる税金
株式売却を行って利益が出た場合には譲渡益課税がかかり、以下の計算式で税額が算出されます。
売却金額ー購入金額(株式購入価格+購入手数料)ー売却手数料=利益
利益×20.315%=譲渡益課税額
例えば、売買手数料が270円の証券口座にて1,000円の株式Aを300株購入し、100万円で売却した場合の利益額は、次のようになります。
100万円ー(1,000円×300株+270円)ー270円=699,460円
699,460(利益)×20.315%=142,095円(税額)
このケースでは、100万円の売却益から142,095円の税金が差し引かれることとなります。
参考:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) (国税庁公式サイト)
参考:株式等の譲渡益の計算方法を教えてください。(SBI証券株式会社公式サイト)
株取引と確定申告
株式の売買取引と確定申告を解説します。納税を目的に年末に行なわれる確定申告ですが、株式投資の利益についてはどのような手続きになるのでしょうか。きちんと理解して自身の投資に役立てていきましょう。
確定申告とは
確定申告とは1月1日から12月31日の一年間の所得税を支払う手続きです。場合によっては支払いすぎた税金が返ってくるひともいます。
証券口座の種類
証券口座の種類をそれぞれ解説します。
- 一般口座
- 特定口座源泉徴収あり
- 特定口座源泉徴収なし
- NISA(ニーサ)口座
証券口座開設の際には、上述の中から種類を選択して口座開設を行うこととなります。これから証券口座を解説する投資家の方は参考にして、効率的な株式投資を行っていきましょう。
一般口座
確定申告手続きを投資家が行う証券口座です。所得金額の算出から納税までの一連を投資家が全て行う必要があります。
特定口座の源泉徴収あり
源泉徴収とは、株式投資から利益が発生した際にはいつでも利益の支払い前に税金が差し引かれる制度です。そのため、特定口座の源泉徴収ありを選択した場合には、投資家は年末に確定申告を行う必要がありません。投資家に代わって証券会社が納税を行います。
特定口座源泉徴収なし
一般口座同様、投資家が確定申告手続きを行う必要がある証券口座です。ただし、株式投資で発生した利益額は証券会社が算出(*1)してくれるため、投資家はその金額をもとに確定申告手続きを行うことができます。
(*1:証券会社によって年間取引報告書という書類が作成されます。)
参考:「年間取引報告書」とは何ですか?(SBI証券株式会社公式サイト)
NISA(ニーサ)口座
確定申告が不要な証券口座の種類です。NISA(ニーサ)は、年間120万円以内の資金で行った投資利益を非課税で受け取ることができる税制優遇制度です。年間の所得税の支払いを目的とする確定申告は、そもそも税金が発生しないNISA口座では必要ありません。
確定申告が必要な場合と不要な場合
証券口座の種類によって異なる確定申告の必要の有無と、その他の場合に確定申告が不要となるケースをお教えします。年末に慌てることがないよう、きちんと理解して最適な手続きを採りましょう。
必要な場合
株式投資を行う証券口座を、一般口座もしくは特定口座源泉徴収なしを選択している場合には確定申告を行う必要があります。
不要な場合
一方で特定口座源泉徴収あり、もしくはNISA(ニーサ)口座にて証券口座を開設している場合には、確定申告は不要です。またその他にも、国税庁が定めたいくらからは所得税納税が必要であるとする基準に利益額が到達しない場合には、所得税控除の対象として確定申告が不要となります。所得税控除は年間の投資利益額が20万円に到達しない場合に該当することとなりますが、住民税の納税は必要となるため忘れずに行うことが大切です。
確定申告をしないとどうなるか
確定申告をしないと、脱税を行ったとして逮捕される可能性があります。納税は国民の義務です。証券会社は投資家の納税状況を税務署に提出することとなっており、納税をきちんと行ったかどうかは国に把握されます。確定申告が必要な場合にはきちんと手続きを行うことが大切です。
確定申告をした方が良い例
ここからは、確定申告を行う必要はないが、行うことで投資家にメリットが発生するケースをお伝えします。以下のケースに該当する場合には、自身の手続きの手間も考慮したうえで確定申告を行っていきましょう。
損益通算
損益通算の結果損失となっている場合には、確定申告を行うことで払いすぎた税金が返ってくる可能性があります。損益通算とは、複数証券口座における一年間の利益と損失を合算して税額を算出することです。
特定口座源泉徴収ありでは、投資利益が発生する度に税金が差し引かれます。そのため、損益通算の結果が損失の場合、本来支払う必要のない税金を源泉徴収にて支払っていることとなります。この際に確定申告を行うことで、払いすぎた税金を取り戻すことが可能となります。
繰越控除
確定申告を行って損失を繰越控除することで、翌年以降の投資利益を繰り越した損失と相殺することができます。繰越控除とは、ある一年間の投資で発生した損失を翌年以降に繰り越すことができる制度です。
ある一年間の投資で発生した損失を翌年以降に持ち越すことで、その後3年間、投資利益と繰り越した損失を損益通算して納税額を減らすことが可能となります。この繰越控除は確定申告を行うことで可能となるため、投資によって大量の損失が生じている場合には確定申告を行うことで賢く投資を続けることができます。
参考:損失の繰越控除(そんしつのくりこしこうじょ) (SMBC日興証券株式会社公式サイト)
配当控除
配当控除とは、配当金に対する二重課税を防ぐ目的で行なわれる税額控除です。配当金は企業が利益の一部を株主に還元するものであるため、法人である企業は利益に対して法人税を支払っていることとなります。そのため、配当金に対してさらに課税されると二重課税の状態となってしまいます。
このような状態を防ぐために、所得税や住民税を一定金額控除してくれる配当控除が設定されており、配当控除は確定申告を行うことでのみ適用を受けることが可能となります。
参考:No.1250 配当所得があるとき(配当控除) (国税庁公式サイト)
パートや無職の場合
ここからは、パートや定職のない投資家の場合を説明します。自身の状況に該当する場合や配偶者がいる場合には参考にしてください。
納税の考え方
年間の給与所得が65万円以下の投資家の場合には、年間で投資利益額が38万円以下であれば納税の必要はありません。パートの給与所得に対しては、給与所得控除として年間で65万円、所得税の基礎控除額として38万円が設定されています。そのため、年間の給与所得から基礎控除額を引き、さらに株式投資の利益額を引いた数字が38万円以下の場合には、所得税の基礎控除が適用されることで所得税の納税が不要となります。(*1)
(*1:「[収入ー65万円]ー株の利益=38万以下」の場合です。)
参考:No.1199 基礎控除(国税庁公式サイト)
参考:No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか (国税庁公式サイト)
参考:No.1410 給与所得控除 (国税庁公式サイト)
一般口座
一般口座では所得税の基礎控除や給与所得控除の適用を受けることで、年間の投資利益が38万円を超えた場合にのみ確定申告を行う必要があります。
特定口座の源泉徴収あり
源泉徴収ありの口座では投資利益が生じた際に毎回税金が差し引かれるため、投資利益額に関わらず基本的に確定申告は不要です。
特定口座の源泉徴収なし
源泉徴収なしの場合には、一般口座の場合同様に年間の投資利益額が38万円を超えた場合にのみ確定申告を行う必要があります。
経費で節税
株取引にかかった経費(*1)を加えて確定申告することで、源泉徴収ありの特定口座を選択していた場合でも払いすぎた税金を取り戻すことができる場合があります。
株取引にかかる経費とは、例えば有料の株式投資セミナーに参加した場合の参加費、パソコンから売買取引を行う場合にはパソコンの購入費やセキュリティーソフト代などを経費として計上することができます。さらに、確定申告の経験がない投資家の場合は過去5年間までの損失を含めて計上することが可能となります。そのため、経費を加えて確定申告を行うことで課税対象となる所得額が下がり、税額の減少に繋がる可能性があります。
(*1:収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことです。)
参考:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) (国税庁公式サイト)
確定申告の必要書類と提出
ここからは、確定申告の際の必要書類とその提出方法を解説します。株式投資の利益に対する税金はどのように確定申告すべきなのでしょうか。これから確定申告を行う必要のある投資家の方は以下を参考にして確定申告手続きを行いましょう。
年間取引報告書
特定口座にて証券口座を開設している場合に、証券会社から送付される書類です。一年間の証券口座内の取引履歴が記されており、確定申告を行う際に必要な、一年間の投資利益額が分かります。
参考:「年間取引報告書」とは何ですか?(SBI証券株式会社公式サイト)
年間取引報告書の内容
年間取引報告書には、売買取引にかかった総額と、利益金額、利益総額に対する源泉徴収額と住民税特別徴収税額が記載されています。投資家はこの書類を参考にして確定申告を行うことができます。
届かない場合
基本的に年間取引報告書は毎年1月中に届くこととなりますが、もしもその期間を過ぎても届かない場合には、場合によっては電子交付サービスにて交付申請を行っている場合があるため、自身の証券会社に確認する必要があります。
申告用紙
確定申告書類を行う際に必要な書類です。申告書には申告書Aと申告書Bの2種類がありますが、株式投資の利益に対する譲渡益課税については申告書Bの用紙を使用して行うこととなります。
また、申告書は国税庁公式サイトからダウンロードする方法、税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る方法、税務署から郵送で取り寄せるという3種類の方法で取り寄せることができます。
参考:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続(国税庁公式サイト)
記入箇所
住所・氏名・生年月日などの基礎情報、所得額と納税額、控除額の欄を記入しましょう。
株式譲渡益の書き方
株式譲渡益は、以下の手順で記入することとなります。
- 収入金額等と所得金額の箇所を書きます
- 所得から差し引かれる金額を記入します
- 分離課税の対象となる収入金額や所得金額などを記入します
- 税金の計算を書きます
確定申告書の書き方の流れを理解して、自身の手続きの際に参考にしてください。
添付書類
確定申告手続きを行う際には、特定口座の年間取引報告書の場合以外にも必要書類があり、証券口座の種類によって用意すべき書類が異なります。
給与所得の源泉徴収票や報酬等の支払い、不動産の譲渡などを行った際の資料をまとめる際の表紙を合計表と言い、必要書類と一緒に税務署へ提出する必要があります。
上場株式等に係る譲渡所得等の金額が必要な場合、つまり税額計算が必要な場合に必要な書類です。
(*1:所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に規定されています。)
参照:国税庁公式サイト 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
本人確認書類の提示又は写しの添付
なりすまし等を防止するために、税務署にマイナンバーの記載がある申告書を提出する際には本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
参考:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い(国税庁公式サイト)
税務署へ提出
必要書類が揃ったら、税務署の窓口に行くか、郵送にて書類提出を完了することができます。
確定申告を正しく行って節税
株取引の確定申告を解説しました。株式投資の利益に対してかかる税金は、証券口座の種類によっては投資家自身が税額を計算して納税しなければならない場合があります。また、給与所得の金額などによって税額控除の適用基準が異なるなど税額控除制度があることで、投資家の状況によって税額の差はもちろん、納税の必要の有無が異なります。このように非常に複雑な税制度ですが、きちんと理解しておくことでお得に投資利益を得ることができる可能性があり、確定申告を行うことで不要な税金が戻ってくる場合があります。株式投資の確定申告と税金についてきちんと理解して、自身の投資に活かしていきましょう。
